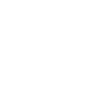- ギターアンプ検証(Marshall JCMシリーズ、JVMシリーズ)
- 2018/06/14
- Category:
ギターアンプの代名詞であるMarshall Ampsの中から往年の定番であるJCMシリーズと近年のモダンヘヴィネスへ一石を投じた新星JVMシリーズを比べてみました。
今回は各シリーズより『JCM 2000 TSL100』と『JVM 210H』をサウンド、操作性、ルックスの観点で比べてみましたのでご覧ください。個性を生かしたサウンド

■JCM 2000 TSL100
まさにロックギターなサウンドという表現がピッタリとくるサウンドです。
それもそのはずで、往年の名曲はこのJCMシリーズのアンプで録音されているものが非常に多く、業界スタンダードなアンプとしてその地位を確立してしまったからです。
TSL100に限定すると母数は下がってしまいますが、Marshallサウンドたらしめている音色の核はシリーズで共通しているため、TSL100はイコール定番のサウンドと言って差し支えないでしょう。
具体的に特徴を上げるとするならば、なんといっても音抜けの良さだと思います。
遠くへ飛んでいく高音と中音、真空管を活かしたマイルドなドライブ感はTSL100の売りで、ギター本来の音を損なうこと歪んでくれることから定番となった理由も納得です。
また特徴的な高音はクリーントーンやクランチとも相性が良く煌びやかな音作りとの相性は抜群です。■JVM 210H
こちらは、TSL100よりもさらに高音域が強調されておりパキッとしたサウンドが特徴的です。
カッティングなどで出したい音域を強調してくれるので、ファンキーなグルーブ重視の曲への対応も得意分野ではないでしょうか。
そしてなんといっても特徴的なのが、従来のMarshallにはなかったRESONANCEのツマミです。
こちらは超低域とも表現される通り、BASSよりもさらに低い音域をコントロールすることができます。
ドロップチューニングされたギターにマッチすることはもちろんのこと、レギュラーチューニングのギターであっても気持ちの良い低域感を演出してくれます。
PRESENSEとRESONANCEをガッツリ上げることで、超ドンシャリなサウンドも作ることができます。
しかし、1人で鳴らす分には気持ち良いのですがRESONANCEはアンサンブルでいうところのベースやキックと同帯域となるので、RESONANCEを上げすぎると低域楽器と干渉する恐れがあります。
ギターとベースで主張する帯域が被ってしまい、文字通りベーシストと喧嘩になんてならぬよう重々ご注意ください。自由度の高いサウンドメイキングを可能とする操作性

■JCM 2000 TSL100
トレブル、ミドル、ベース、ゲイン、ボリュームの基本的なツマミを12時方向に回せばザ・マーシャルサウンドの出来上がりです。
そのくらい定番の音を作ることが容易な点は、常設してある商業スタジオやライブハウスの多さから伺い知れます。
場合によってはサウンドメイクよりも、真空管を暖める時間の方が長いなんてことも冗談抜きにあり得ます。
TSL100に限ると常設している施設は多くはないかもしれませんが、無印のJCM 2000と基本は変わりませんので高い操作性を発揮します。
コントロール部に関しては、無印のJCM 2000よりも細かいコントロールが可能です。
というのも、CLEAN、CRUNCH、LEADとチャンネルごとに個別にイコライジングすることができるのです。
その分複雑なのかというと、そういうこともなく基本的なツマミが多く並んでいるだけなので直感的な感覚は損なわれません。
また、常設している施設が多いと前述しておりますが、それは言い換えると替えが効くということです。
急にスタックアンプが必要になった場合に利用方法が多いという強みが、ある意味一番の必要なのかもしれません。■JVM 210H
CLEANとOVERDRIVEの2チャンネル仕様ですが、それぞれ3段階の切り替えが可能となっており形6種類のモードを選択することができます。
イコライジングはそれぞれのチャンネルに紐付いた作りとなっており、トレブル、ミドル、ベースが2種類ずつあります。
基本の音を作るだけなら、JCMシリーズとなんら変わらないため前述したサウンド面の違いが大きいかもしれません。
一方、少しだけ複雑にはなりますがMIDIでの操作などが可能となっておりJCMシリーズよりも複雑なことが実現可能です。
MIDIコントロールのツマミやRESONANCEなどあまり馴染みがないと小難しい印象を抱くという側面がありますが、現代のギタリストが求める理想に対するMarshall社の回答ではないかと考えられます。
また同シリーズから販売されている410Hは4チャンネル×3モードとさらに幅広い音作りが可能となっています。
興味がある方は、JVMシリーズ同士で弾き比べてみても面白いかもしれません。伝統的なマーシャルルックス

Marshallのアンプは、まさに王道のギターアンプです。
音楽に詳しくない人でも、ロックギターのアンプで想像するルックスはMarshallのアンプだという方も多いと思います。
そんなルックスを継承しているTSL100とJVM 210Hですが、細かく見ていくと当然違いが見られます。
個人的に一番の違いを感じた部分はツマミの並び方です。
それは前述したチャンネル数やRESONANCEの違いにより、ツマミの設置場所や並びが全く違っているからです。
TSL100は全体へ影響するコントロールは左側、各チャンネルごとのトレブルやミドルなどを真ん中2列と右側に分けて設置しています。
一方JVM 210Hは全体へのコントロールは真ん中寄りの左側、トレブルやミドルなどは右側に2列設置となっています。また両アンプとも2列になっているツマミがありますが、これはツマミを操作する際にもう一方の列を誤って操作してしまうリスクがあります。
この点に関してJVMシリーズはツマミの列同士の間隔が広く取られています。
そのためにツマミの設置されているコントール部の面積がJVMシリーズの方が広くなっているのも特徴です。この違いは恐らく、アンプという商品の使い勝手や国ごとの利き手の比率や国ごとのマーケットの違いを考慮して設計されていることが伺えます。
アンプ業界最王手のMarshall社の歴史が少し覗けるような気がして非常に興味深い違いだと思われます。まとめ

今回の検証ではギターリペア工房DNS-Draw a New Sound-のDNSカスタムギター『Rainy』を使用しております。
シングルPUのキレがありながらファットなサウンドが特徴で、Marshallとの相性も素晴らしくオケの中でも埋もないサウンドです。様々な観点で比較検証をしてきましたが、一概にどちらが良いとは言えません。
というのも、求めるアンプの答えは十人十色であり、どちらのアンプも誰かにとっての一色になる可能性を十二分に秘めているアンプだからです。
どちらのアンプも実際に触れる機会は多いはずですので、後はご自身で触ってみて違いを体感していただければそれが最も最適解となるのではないでしょうか。
今回はMarshallのJCMシリーズとJVMシリーズを比べてみましたが、好評をいただければ別のアンプを比べたりするかもしれませんので楽しみにしていただければ幸いです。Marshallを始めとした豊富なギターアンプでレコーディング出来るCPR STUDIOはこちら
【関連記事】
⇒Diezel Herbertを導入しました。
⇒ギターアンプ(Marshall JCM2000 TSL100)を導入しました。
⇒ギターアンプ(Mesa/Boogie Dual Rectifier)を導入しました。
⇒ギター用ヘッドアンプ(Koch Powertone PT-120)を導入しました。
⇒ギターアンプ(ROLAND JC-120)を導入しました。
⇒ギターアンプ(Fender Twin Amp)を導入しました。
⇒キャビネット(BASSON B412)を導入しました。
BLOG CATEGORY
- すべて
- COMPILE RECORD
- CPR STUDIO
- お知らせ
- COMPILE RECORDからのお知らせ
- CPR STUDIOからのお知らせ
- SOLUTION
- SOLUTIONからのお知らせ
- DESIGN
- DESIGNからのお知らせ
ARCHIVE
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月